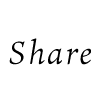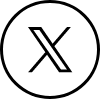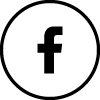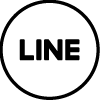山小屋の窓から見えるもの
男の隠れ家 (夏、山へ。2020) 掲載

雲ノ平は北アルプスの最奥地に忽然と広がる溶岩台地だ。標高2600m付近に広がる平原には、まるで庭師が神の手を借りて庭園を誂えたかのように、池塘や火山岩、ハイ松などが、穏やかで均整のとれた風景美を織り成し、周囲を取り囲むように居並ぶ峻厳な山々と不思議なコントラストを描き出す。冬は一面の雪原、春は花が咲き乱れ、夏には蒼く、秋には黄金色の草原が風になびく、季節の移ろいは圧倒的な変化に富んでいる。
その中心部に雲ノ平山荘はある。
自然保護思想
山小屋は、自然と人間社会の関係性を創造する前線基地であると僕は考えている。
なぜ僕らは山に行くのだろう。
自然界では、あらゆる色彩や造形、変化や調和、生と死のもたらす無限の物語がたえず繰り広げられ、機械的な世界にとらわれがちな僕たちの意識を、あるがままの、謎に満ちた世界に解き放ってくれる。
アウトドアレクリエーションを趣味や娯楽のいちジャンルとみる人もいると思うが、それは断片的な見方に過ぎない。自然から生命の実像を学び、社会にそのインスピレーションを還元するために、最も不可欠な行為が「そこに行く」ということであり、最も効果的な学び方が「遊ぶ」ということだっただけである。自然から得られた創造性は、アートになり、自然科学になり、機械工学や都市デザインになり、バイオテクノロジーになり、人々の生き方そのものになる。
そして、自然を体験するための仕掛けが国立公園などの社会制度なのだが、それは19世紀に欧米で台頭した自然保護思想に由来する。
思想といっても、高尚な理論が先に存在していたわけではなく、産業革命を皮切りに急速に拡大した開発圧によって脅かさた歴史的文化、景観などの生活環境を市井の人々が自らの意思で守ろうとする運動が、自然保護思想に実を結んでいった。
自分たちのアイデンティティーであり、基本的な人権として「自然は必要だ」という意思が、明確に共有されたのだ。そして、その議論に芸術家や思想家、アルピニスト、学者、政治家などが合流する中で、それぞれの分野の理念を織り込みながら発想を展開し、より純粋な形で「自然そのものに学びを得る」機会を、将来にわたって失わないようにするための象徴として「国立公園」という社会制度を生み出した。自然保護とは生活と地続きの人権運動なのだ。
現代においても、疑いようもなく自然の存在は、人々が共有し得る数少ない普遍的な価値だ。経済やテクノロジーが競争や対立、破壊と常に紙一重であるのに対し、自然はあらゆる生活やクリエーションの源であって、何を失っても立ち返ることのできる人類の古里である。山小屋の存在意義は、このことにこそ立脚するものだ。

日本の国立公園
しかし、先進諸国の国立公園が、長年の熟議を経て合理的な制度を獲得しているのに対し、日本の国立公園は、逆境に立たされ続けている。年間1000万人近い来訪者がいる北アルプスでさえも、公的な予算や人材が著しく欠乏し、自然保護のシステムも脆弱なのだ(※1)。
歴史的にこの国では、人権の問題としての自然保護思想が社会に根付かず、国立公園の存在意義が市民権を得られていない。
大正時代には、日本でも一部の知識人たちの間で花開きつつあった独自の登山文化を背景にして、洗練された国立公園の設立を目指す運動も展開されていたのだが、当時はむしろ殖産興業、富国強兵に湧き立つ時代だった。江戸期まで連綿と培った自然に遊ぶ多彩な生活文化は鳴りを潜め、各地では自然破壊を伴う巨大開発が進行する中で、上高地すらもダムに沈みそうになっていた。候補地が消滅してしまっては元も子もなく、とうとう公園の設立を目指す人々も、十分な財源や世論の支持を得て高度な国立公園を立ち上げるという計画を諦め、次善策として「国立公園は財政的な負担をかけずに作る」「維持管理も当面は民間事業者が手がければ良い」「観光利用で経済は潤う」という論点に切り替えて政治家を説得し、景勝地の水没だけは避けるべく緊急避難的に成立させたのが、「安上がりな」日本の国立公園だった。
このような背景のため、日本の国立公園制度は概して観光産業的で、公的な自然保護システムが希薄なものとして成立し、その状況は未だに続いているのだ。登山は流行ったが、自然保護は流行らなかった、というアンバランスなのである。
山小屋が抱える問題
かくして、北アルプスでは山小屋や猟師、登山ガイドが切り開いた道がそのまま山岳地図になり、以来、主には山小屋が登山インフラ全般を支えてきた。山小屋の仕事は多岐にわたり、宿泊業全般、緊急避難場所であることにはじまり、登山道の維持管理、遭難救助、学術機関や行政の活動拠点、各種情報発信、行政との様々な折衝に至るまで、山に関するあらゆることと言っても過言ではない。これまでは、登山文化は山小屋文化と一体だったのだ。
そして、この構図は今、明らかに限界を迎えている。
ライフラインであるヘリコプター会社の業務撤退、建設費の急騰、人材不足、追い打ちをかけるコロナ禍などにより、山小屋の業態そのものが存亡の危機にさらされている。現実問題、次建物が老朽化した時には、建て直すことは採算が取れない事業になる可能性が高い。異常気象による登山道の荒廃も加速化する中、山小屋が事業として成り立たなくなったら、誰が登山インフラを維持していくのか。このことは大きな疑問符としてのし掛かってきている。「山小屋を守る」という情緒的なことではなく、これは国立公園の持続性の問題であり、人々と自然の関係性の問題であり、登山文化のもたらす社会経済の創造性の問題として、どう捉えるかである。誰かに引き継ごうにも行政に現場を知っているエキスパートはほとんどおらず、また自然保護が職業として成立しておらず、自然に関する学問の分野も育っていない現状でできること。それは「皆で考えはじめること」しかないだろう。登山者や一般世論、行政や関係事業者の垣根を取り払い、私たちにとって「自然とは何か」という視点に立ち返り、社会のあり方から見直す時期が訪れている。
無論、人が来なくなれば自然が戻る、という単純なことでもなく、社会に注目されなくなれば、また自然破壊が台頭する、人類の歴史はこの繰り返しなのである。
これからの世界へ
気候変動、資源の枯渇、持続可能性、資本主義の限界など、現代の主要な社会問題はその多くが自然とは何か、という問題に接続している。折しも猛威を振るうコロナ禍も同様であり、急激に変化する自然(生存)環境を柔軟に読み解く力が問われている時代である。
自律分散型の社会を志向する動きも出てきているが、日本は長い間正反対の方向にひた走ってきたのは事実だ。都市の過密化と地方の過疎化が絵に描いたように同時進行し、どちらの生活環境も悪化する中、田舎( ≒自然環境)は都市の出先機関として軽んじられ、工業用地に変貌を遂げてきた。結果として、あらゆるレベルで土地に対する愛着が失われ、精神的な基盤が深層から疲弊することで、都市も地方も共倒れしかけているように見える。
今こそ、価値観をアップデートする時期なのではないだろうか。
持続可能な社会とは、多くの人々が「このままでありたい」と積極的に望む状況であり、それは間違いなく「美しさ」という視点が欠かせない世界だと考える。
自然とはなんだろう。
山小屋が、その視点をもたらす一助になれば幸いだ。
(※1)北アルプスにおける環境省の自然保護官の人数は、同等の規模や経済効果をもつアメリカ及びヨーロッパ諸国の国立公園の10~50分の1程度。