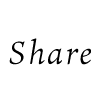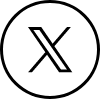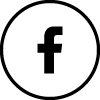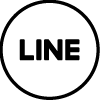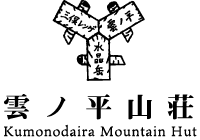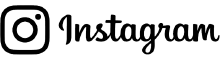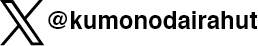きっと雲ノ平では今頃、一面に広がる雪原の冷気の中を縫うようにして、どこからともなく春の暖かな風が漂ってきていることだろう。もうすぐ夏山シーズンだ。巡る歳月の速さを感じながら、僕たちも気ぜわしく小屋開けの準備に取り掛かっている。皆さんはどんな計画を立てているだろうか。
今回はこれから先、アウトドアスポーツや自然を楽しむために、多くの人と共に考えて行きたい事について話そうと思う。端的に言えば、日本では自然環境を楽しんだり利用する力は大きいのに対して、それを維持し、末長く守っていこうという力があまりにも不足している状況がある。それをより創造性のある方向へと舵を切ろう、という話である。少し社会的な内容になるが、とても身近なことだ。また僕の経験上、話の内容が雲ノ平山荘を取り巻く中部山岳国立公園(北アルプス)を基準にしていることを付け加えておきたい。
登山道と山小屋
まずは全体の起点となる話題として、登山道について触れてみようと思う。
あまり体系的に語られることはなかったが、二十世紀初頭に端を発する日本の近代登山の黎明期に、原野だった山々を誰しもが登山をできる環境へと切り拓いたのは各地の山小屋創業者や猟師、山案内人などの個人、あるいは信仰登山の延長線上の活動よるところが主たるものだった。それらの活動が発展して国立公園の地図になったと言っても過言ではなく、当初から行政の関与は限定的なものだった。その構図は現在もほとんど変わらずに引き続いており、日常的な登山道整備をはじめとする国立公園の公共的機能の多くを山小屋が担っている。しかし、ほぼ一世紀に渡って利用されて来た登山道の状態は、近年のゲリラ豪雨等の異常気象も影響して悪化の一途を辿っている地域が数多くあり、山小屋だけで受け持つのは限界を迎えつつある。それは言わば山小屋という個人の能力や感覚、経済力に依存した状況であり、国立公園という本来公共性の強い資源を、地域差がなく安定した形で存続させるためにはあまりにも脆弱な仕組みであると言わざるを得ない。例えば、従業員が3人しかいない山小屋と同30人いる山小屋が同等の広大なエリアの登山道を整備している、という事実からもその仕組みの危うさは容易に理解することができるだろう。登山道の状態は登山者数に加え、地質や気象条件など、複合的な要因が強く作用して明暗を分けるため、奥地の小さな山小屋の周辺だからといって安定している訳ではない。当然経済基盤の弱い山小屋は満足に登山道を維持できなくなる可能性は高くなってしまうのだ。
無論僕個人として登山道の整備を投げ出したいということではない。他人には任せられないという自負や愛着もあるし、自然に縁遠い業者が手がけることも多い公共事業は信頼性に欠けるのも事実だ。雲ノ平山荘としては10年前から東京農業大学と共同で荒廃地の緑化の研究を始めている。誰しもが実践できるケーススタディとして展開していきたいと思っている。
だがこの問題はただの仕組みの危うさでは片付けられない様相も呈し始めている。近年の山小屋の経営環境の変化である。設備費、資材運搬費等の著しい高騰、装備の発達で小屋泊が減りテント泊に移行している現状、スタッフの人材不足(ブームでも山小屋で働きたいと思う人は減少している。ある意味で“変わらない山小屋”と多様化し“変わっていく登山者”の利害が乖離してきている)など、山小屋経営を取り巻く状況は不透明感を増しつつある。経済のバランスの先行き次第では、力の弱い山小屋は現存の建物が老朽化して建て替えようとした時、建設工事が事実上採算の取れない事業になってしまう可能性すらあるのだ。万が一山小屋がなくなれば、登山道は一体誰が面倒をみるのだろう。これは極論だが、いずれにしても登山を文化として盛り上げるためには、社会の共有財産として改めて”国立公園”のあり方を考える時期がきていると思う。
日本の国立公園
この状況の背景には、日本の自然環境をめぐる社会の姿勢や国立公園の成立に至るまでの経緯が深く関係している。日本ではヨーロッパで隆盛したアルピニズムに触発されて、アクティビティーとしての登山は大衆的な広がりを見せた一方、西洋社会でアルピニズムと前後して高まった自然保護思想は根付かず、現代社会における自然の持つ重要性を広く共有する活動は行われてこなかった。結果として、現在に至るまで日本では自然環境全般に関する世論は極めて弱い。(国立公園に限らず、人間社会と自然の調和や関わり方についての議論自体が希薄だ。自然保護の思想は人間社会の豊かさの大きな指標でもある。人間を大事にしない社会で、まず自然から守ろうという順番にはなりづらい。)
現に日本の国立公園はアメリカやヨーロッパ諸国のシステムを参考にして設立されたものだったが、自然保護思想、すなわち自然そのものを尊重する考え方を社会に根付かせる過程が十分になかったために、自然の価値に重きをおくというよりは、昨今の世界遺産誘致活動にも類似した、観光政策としてネームバリューをつけることに傾斜していた感が否めない。欧米諸国では自然保護思想や、自然科学(博物学)、アクティビティーとしての登山が同時並行的に発展し、それらのパワーバランスを良い状態に保つために活発な議論が展開されてきたのに対し、日本では思想や学問にまつわる世論は非常に弱く、レジャーとしての登山が偏った形で大衆的な広がりを見せてきた。結果的に自然の魅力や現状を国民に対して客観的に伝え、共有するために不可欠な科学的、学問的なアプローチが乏しく、原生自然を扱う技術や見識も、それらにまつわる人材を育むための仕組みや国立公園に対する予算も圧倒的に不足している状況が続いている。行政の積極的な関与が少なかったために独自の山小屋文化が発生したという側面もあるが、様々な事柄が臨界点を迎えていることは前述の通りである。
端的な理解を促すために日本の国立公園の特徴的な事柄を以下にまとめてみよう。
日本の国立公園の指定は”地域性”という方法に基づいている。これは歴史的に多様な土地の権利者が混在していることから、土地の所有は一元化せずに自然公園にふさわしいと評価された一帯を公園に指定する方法だ。同じ方法をとるイギリスなどは寧ろ民衆の間から自然、文化保全の機運が高まったため、地域社会と行政、NPOなどがコンセプトを共有し役割分担をすることで寧ろ合理性という意味でも相乗効果を生み出す仕組みを作っている。しかし日本の国立公園では残念ながらそもそもの目的が曖昧であり、利害の噛み合わない縦割り行政の弊害が目立つ。地主は林野庁、自然保護は環境省、河川は国土交通省、ダム周辺は電力会社、公共事業の受け皿は地方自治体など、それぞれが異なる法律や目的を持って混在しており、意見を集約する仕組みもない。その中で環境省が最も立場が弱い組織だと言っても過言ではないのだ。各地の自然環境が国立公園に指定された後に様々な大規模開発にさらされたのもこの構図が大きく影響している。
また国立公園の運営を規定する自然公園法の体系も、近年少しずつ改善傾向はあるが、能動的に自然環境を扱う仕組みを有さず、(受動的な)規制によって風景を維持することに偏重している。いわば行政は積極的に関与しないことを前提にして、開発圧に対して様々な規制を設けることにより、壊されないことに期待するという姿勢なのだが、既に多くのことに無理が生じつつある中では、行政もより能動的、科学的に関与していく体制を作ることが急務だ。体制ということでは日本では国立公園は環境省の末端的な業務として取り扱われており、アメリカにおけるナショナルパークサービス、イギリスのナショナルパークオーソリティーのように国立公園を専門的に扱う独立性の高い機関が存在しないことも現状を端的に物語っている。
人材不足は殊更に深刻な問題だ。北アルプス全体をとっても環境省の正規職員であるレンジャーは5人しかおらず、彼らもほぼ2、3年ごとに異動してしまう仕組みになっているため、実践的なエキスパートが育たたない。登山道をはじめとした各地の現状把握すらも困難だ。いくらレンジャー個人に情熱があったとしても、この人員数、人事システムが立ちはだかっていては現状を打開するのは不可能である。またこの異動の仕組みは他の役所も同じで、ほぼ全ての役所の担当者が3年もすると総入れ替えになり、それだけでも多くの話が後退、霧散を余儀なくされる。「記憶にございません」「記録が見つかりません」「経験も思い入れもございません」の世界観はここでも猛威を振るっている。
国際的に自然公園の指針というのは利用と保護のパワーバランスで決定づけられるものだが、客観的に見て日本の現状はどうなのだろう。情緒論に陥らないようにここで簡単に国際的な自然公園の管理体制や規模の比較してみよう。分かりやすい指標として、レンジャーの数、予算、来訪者数、経済効果などを見てみたいと思う。単純比較は難しく、あくまでも概要である事はご容赦願いたい。(下の表参照)

やはり驚くのは北アルプスに915万人(これも推計のレベル)も訪れているのに、正規職員が5人しかいないことだ。日本の自然環境はイギリスの単調なそれよりもはるかに複雑で手が掛かるし、探求しがいもあると思うのだが…。各国立公園にかける予算を非公表にする理由も理解に苦しむし、費用対効果のバランスを見る上で経済効果を認識することも不可欠だろう。国内でも地域社会との連携を進化させつつある事例なども出てきてはいるようだが、大局的には保護のベクトルは人混みに掻き消されそうである。
また、国立公園に関する資料を集める中で強く感じたのは、日本の国立公園の情報発信の貧しさである。アメリカ、イギリスに至っては各公園毎に、生態系の変遷、地域社会、NPOなどとの連携、公園内の文化財に関するの活動報告、公園の利用者数や経済効果など2、300ページに及ぶ詳細なレポートを毎年発行し、それをもって国民に対して国立公園の価値を知らしめるとともに、国立公園の予算への理解を得る努力をしているのに対し、日本では、容易に閲覧可能な資料自体が非常に乏しいし、閲覧できるもとしても内容が薄っぺらいものが大半のように見受けられる。体系的にまとめてある資料といえば「自然公園の手引き」という一般財団法人が発行する書籍があるが、国立公園の他無数にある国定公園や県立公園も含めたものとして400ページ弱、内容に至っては前年の焼き直しの一般的な事実確認が大半を占めている。もしかしたら学術論文などで良い資料も散在しているのかもしれないが、国民が日常的にアクセスできる状況とは間違っても言えない。情報がない中で世論だけ機能するというのも極めて困難だろう。
登山ブームと情報
最後に登山を取り巻く情報のあり方について触れたいと思う。現在は第3次登山ブームと呼ばれている。ブームというのはどこかその終焉も内在してしまっているように思われるので、僕は何だか寂しい響きに感じる。これまでも日本の登山は第一次登山ブームから現在に至るまで、様々なブームで彩られてきた。アルピニズムに始まり、山の歌、百名山、ワンゲル、中高年、トレランetc、どれがいいとか悪いではなく、その度に登山者層が大きく変わり、多くの場合時代毎の登山のスタンスの違いから新しい時代を懐疑的に見る人達が現れたり、現場にささやかな混乱が生じたりする。しかし考えても見ればどのブームも20年とは続いていないし、新しい世代に苦言を呈する人達にしても、その時代なりの問題が山積していたはずだ。またどのブームでも決して“自然”そのものは主役にはならず、キャッチコピーや登山スタイルに重点が置かれてきた。ブームでなくとも、常に性善説的な表現に縛られた、観光的なアプローチが強かった。僕が本当にもったいないと思うのは、その連続性のなさと根っこのなさだ。上述したように全ての人が喜びの源としているはずの自然を扱うシステムには多くの問題があって、それを変えられるのは唯一世論でしかない。しかしブームを意識すると、どうしても入門者におもねる傾向が強くなり、情報発信のあり方が短期的なインパクトを重視してしまう為、表層的な紹介の範疇を脱却できなくなる。そのスパイラルだと、どうしても国立公園制度の問題とか、登山を取り巻く経済の話、自然環境の本質的な魅力を共有するところまで到達しない。(またサービス業としての山小屋情報に偏りすぎると、いたずらに山小屋の格差を助長しかねないし、山小屋側の意識もおかしくなる…)これら全ての構造が寧ろブームを短命に、ブームのまま終わらせる原因となってしまっていると思う。身近な話としても、現実が後手に回っているインバウンド招致や後期高齢化する登山者の安全問題にしろ(インバウンドについては別途書きたいと思うが、例えば北アルプス地域の登山口までのアクセス一つとっても、マイカーかタクシーでしか行けない場所の多さや英語表記の有無など、論外とも言えるような状況は多い。高齢者登山についてはツアー登山の危うさなどがある一方で、歳をとる意識そのものの話だったりするので大きな議論が必要だろう。そして根底には人里の生活環境の悪さが登山を卒業できない根深い構図を生み出しているのではないだろうか…)、今のシステムや情報の質では対応できないだろうし、経済効果さえも引き出しきれないだろう。行政の情報の質の低さもさることながら、情報を求める世論も存在しないとなれば、どのように実りのある議論ができるというのだろう。とかくインスタントに名前を売ろう、儲けようという文脈ばかりが目立つが、経済を重視すればこそ、情報の質の向上と持続性を真剣に追求するべきだ。
ただ、実は僕は今回のブームには密かに期待している。なぜなら本格的な情報化後の初めてのブームだからだ。現代人はかつてに増して自然に足を運ぶ理由を溜め込んでいると思う。生身の人間が許容し切れない情報量、自由と言う名のプライバシーの喪失、日々の際限のない高速化、殊更に世代を超えて共有する価値観や文化的基盤を失ってしまった日本社会の寄る辺のなさ。何か普遍的でシンプルなものに回帰しようとする意識は日増しに強まっている。だからそれに対して山小屋も普遍的な美しさで応えたいと思う。自分も同じ世界の住人として。
正直に言えば山小屋とて消費的登山文化の一端をなしてきた存在でもある。確実な世界観や哲学があるでもなくブームにあぐらをかいているだけでは、情報化や経済難の中で多くを悩み、選び、生き抜こうとしている若者が格別山小屋に肩入れしようなどとは思わないだろう。今は未来に引き継ぎ得る考え方を作る時期だ。(だがここでも残念ながら、ブームにあやかって国の各種機関、地方自治体、NPOなどが独自の観光政策や規制案などを、縦割りを絵に描いたような状態で百出させ始めている。)
大切なことだからこそ、性急に答えを出すべきではない。僕たちに必要なのは架け橋だ。登山者と山小屋、行政やメディア、学識経験者など、あらゆる人が同じ地平に立つための架け橋。そして未来の人々への架け橋であることこそ忘れてはならない。山小屋に担えるのはその役割ではないか思っている。
批判がましいことを言ってきたが、僕は互いに意見を言えるようになる事がスタートラインだと思う。そして誰も敵対関係ではない。寧ろどうやって分断されている力を繋ぎ合わせることができるのか、この国の誇る登山文化や自然環境の魅力を最大限に引き出せるのか。そのことだ。
これからが旅の始まりだと思う。