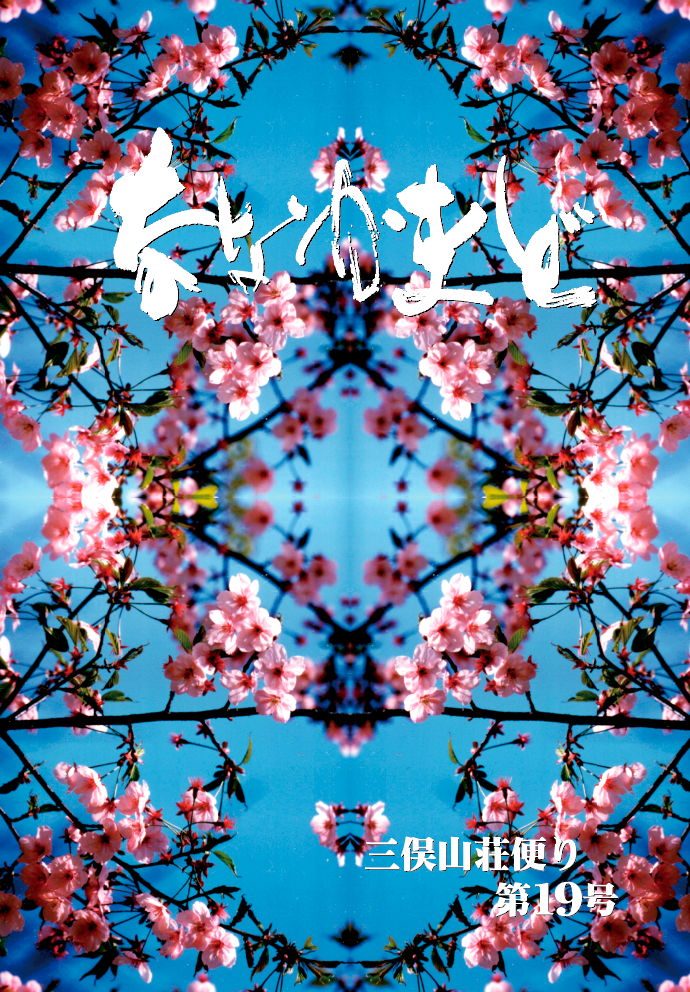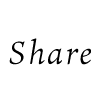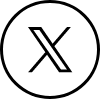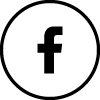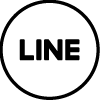美しさと虚しさ
ななかまど19号(2016年発行) 掲載記事 - 伊藤二朗=文・写真
風に乗って、ふと枯れ草の匂いがする。
するとその匂いが脳裏に沈んでいた遠い記憶を呼び戻す。
どこかの異国の夜明け。
小さな村の未舗装の道を、突っ掛けを履いた女たちが行き交う。
平原のかなたの丘陵から昇り始めた朝日が、夜露に濡れた木立を白々と照らし出す。
秋なのに暖かな日。
その景色を僕はバスの窓越しに見ている。
懐かしい旅の匂い、そしてその光の余韻…。
不思議なものだ。覚えているから遠退いて行くことと、覚えているから近く感じる事。
時間や距離を越えて、何か突拍子もないものが近くに寄り添っていたりする。
僕はもっとクリアにこの世界を見てみたい。
その為には透徹したまなざしが必要なのだろう。さりとてあまり踏み込みすぎると恐ろしいようでもある。物事の価値や意味など、ぎりぎりのところに浮遊しているに過ぎないのだ。
いつだったか何となしに仏教に関する本を読んだ事を思い出す。
仏教の概念によると、この世界は表裏一体の二つの側面から成るという。
ひとつは見えない空の器のようなもので、微動だにせず在り続ける空間そのもの。
もう一方は物事が生じ、消滅する事の絶えざる連鎖であって、それが一種の流れとして捉えられ、いわば空間(静)に対する動となり、僕たちに物事の存在を認識させる。これを人は時と呼ぶ。そして生滅を繰り返すそれらの“物事”は、あくまでも現象であり、実体として捕らえ得る堅固なものではない。幻のように過ぎ行くものだ、と。
それはそうだ、と思ったものだ。その感覚は事実、いつからともなく僕にとっては日常の景色の根底に流れているものだった。
消滅(終わり)がなければ存在(現在)もなく、時も、意識もない。(やや視点はを変えてみると、この見方は例えば多くの破壊が起こる動乱の時代ほど、社会に画期的な思想や技術が生まれるものだし、ありふれた物事を再評価したり、行き過ぎて執着を深めたりする、といった事象にも通じるのではないだろうか。大きな変化に晒されるほど“意識”は先鋭になる。)そして意識的になるほどに人間は実体のない時という何物かに触れようとして懸命に走り、やはり触れる事が出来ないからこそ、また走る。不足が常に原動力であるのと同時に、追いかけているのは“消滅する”事の観念のようなものであり、いつまで経っても追い付き得るものではない。
しかし消えても、消えても、世界は存在する。
消えるほどに存在する。
果たして消えるものは何なのだろう?
ブッダ自身は、上述のような思想に立脚しつつ、論理に執着してはならないと戒める。世界の虚しさを知る事は、際限なく繰り返される数多の混乱や、苦しみの連鎖から本質的に距離を置く為にこそ大切なのだ。さればこそ許したり、理解したりする事ができる。真の自己を確立できるのだと。
僕は仏教徒ではないし、欲にまみれた人間ではあるが、仏陀という生身の人物が、歴史の闇のかなたから投げかけるその静かなまなざしに思いを馳せることがある。
とらわれないということだ。

それはさておき僕は今、森の中に居る。
先程まで降りしきっていた雨も止み、夕闇が迫る辺りでは、高い木立の枝葉から落ちる水滴が、一面の笹の葉をぱらぱらと鳴らしている。
9月のシルヴァーウィークの祭り騒ぎも終わり、束の間の休暇をとって高天原の奥地の大森林帯を目指したのだ。雨の道中、青い霧が立ち込める龍昇池や、色とりどりに紅葉したななかまどやミネカエデが、この世ならざる美しい情景を見せていた。山水画のように頂を影だけ浮かび上がらせる薬師岳を横目に、藪をこぎ、木の根に躓いて転げながら夢の平を越え、崩壊した白砂の壁のような湯の沢を渡り、急斜面を笹に捕まりながら這い上がると、忽然と深く静かな森である。
その森で、僕は驚くべき大木に遭遇したのだ。
樹齢二千年にもなろうかと思われるネズコの木。
大昔に落雷にあったのだろう。主たる幹は空洞となり、生き延びた一部が今や巨大な枝葉を暗がりに張り巡らせている。
雨に濡れた樹皮は赤黒く鈍い光を放ち、岩壁のように猛々しく波打っている。
地面などなく、宙にただ独り立っている者のように、その木は存在している。
生命そのものであり、時そのものとして。
僕はただ歓喜とも畏怖ともつかぬ思いで、その場に立ち尽くすだけだった。
その木から遠からぬところに一夜の宿りを定め、僕は夕闇の中で森のざわめきに耳を澄ましているのだ。
ともあれ、ここでは普段僕が幻と戯れる如くに思いを馳せる“時”が当たり前のように展開している。元から定まった形などは存在せず、生滅の絶えざる変容こそが森と呼ばれる。春に雪が解けて芽を出し、まばゆいばかりの新緑がいつしか黒々と深く、重くなり、やがて鮮やかに色づくのも束の間、落ち葉となって雪に沈む。
世界は自分の名を書く暇などなく、変容している。
誰が操っているわけでもなく、自律的に、しかしどうしようもなく。
生きているものも、そうでないものも。
自然に癒されるというのは、時から開放されるからなのか。
自分であることの意味や、消え行くものを数える事の悲しさを、それとなく和らげてくれるからなのかと、ふと思う。