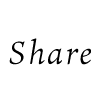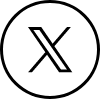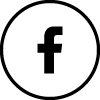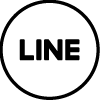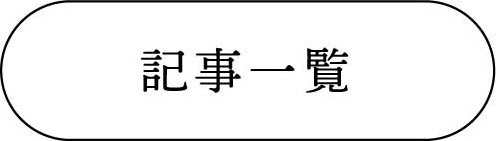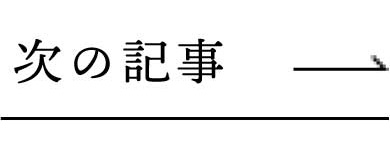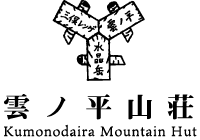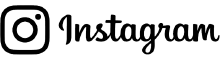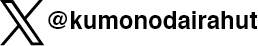山と僕たちを巡る話
第6回
ミャンマーから
北アルプスの最奥、黒部・雲ノ平での暮らしから垣間見えること。
かつての日本の姿と重なる彼の地で思う、『黒部の山賊』の時代。
今回は少し番外編になる。僕がいまミャンマーにいるからだ。旅先にコラムの作文を宿題として持ってきてしまったものの、なかなか日本に意識を戻すのが困難である。それならばせめて目の前にある景色から浮かび上がる雑想に日本への想いを重ね合わせてみようと思う。
僕にとってミャンマーを訪れるのは3度目のことだ。最初は2010年、雲ノ平山荘の新築工事が終わり、心機一転新しい風を欲していたときに見た一枚の写真がきっかけだった。それは、広大な平原に無数の、ピラミッドを彷彿とさせる大きな仏塔や寺院が立ち並び、西日を浴びて燦然と輝いている情景。日本の平安時代のころに花開いたバガン王朝の大仏教遺跡を捉えたもので、僕はなぜか即座に「ここに行こう」と思い立った。だが当時はまだ彼の国が軍事政権により国際社会に対して閉ざされている時期で情報も少なく、ましてやアジアの国を訪れること自体が初めてだった僕にとっては博打のようなものでもあった。そして、結局その魅力にほだされたのだ。
なにに魅了されたのか? それをひと言でいうのは難しい。ミャンマーを訪れた日本人が少なからず語る思いが「得も言われぬ懐かしさ」であるという。そうかもしれない。なにがそう思わせるのかといえば、人々である。仏教の内省的教えの影響か、民族性か、これこそ定かではないが、はにかみ屋で穏やか、実直そうだが本心はわかりづらい、いわゆる古き良き日本人についていわれがちな気質を感じることがよくある。
そして彼らの生活。電力は乏しく、暗い未舗装の道の電柱の下で、小さな子どもたちが夜更けまで転がるように遊び、軒先から親たちがそっと横目で見守っている情景や、バラック作りの工場で鍛冶職人が一心不乱に赤く熱した金に槌を振り下ろしている姿、一面の水田にポツリと建つ質素な木造家屋、田んぼに佇む若い男女と牛車、大地と人間の境界線が朧げな世界。政治や社会システム、科学技術に規定される前の「人間」の情景である。子どもたちの姿などを見ていると、必ずしも子ども好きではない僕ですら、その美しい眼差しにちょっとやられてしまう。
これは、どこか普遍的な郷愁であって日本人に限った感覚ではないのかもしれないが、彼らの姿を目の当たりにして胸をよぎるのはたしかに大正、昭和初期の日本への幻想だ。それは僕にとっては父が語り草にしていた世界である。民族や場所も変われば時代の進行自体が大きく違う。異国に赴いて自分の常識がまったく通じない現実を目撃することで、あらためて生きるということを捉え直す機会になる。旅の効能とはそういうことでもあるのだろう。 先日も西部のラカイン州の人里離れた山道をバスに揺られながら、窓外で人々が道路の舗装作業をしている場面を見かけた。村人たちが、大きな岩石をハンマーで砂利状になるまで細かく砕き、それをみんなで道路に敷き詰め、道を作って行く。なごやかに談笑しながら作業をしているが、バスで丸々半日もかかるような険しい峠道を万事その調子で仕上げていくわけだから、一体どれくらいの時間がかかるのだろう。しかし、彼らはそれを「気が遠くなる」ようなことだとは思っていない。

思えば『黒部の山賊』の時代、100㎞もの重荷を背負って山道を闊歩していた歩荷や、鉱山労働者たち、猟師たちも、このような人たちではなかったのか? 他に選択するべくもない現実を無心に、ひたむきに生きる、その姿は掛け値なしに輝いている。生活と労働、自然と人間、自分と他人との境界線すら明瞭でない、大きな時のなかにいる人々。素朴な美しさというのは、そのような時のなかに潜んでいるのではないだろうか。
ひるがえって、日本という国はいまどこにいるのだろう。素朴であることを過ぎると、とかく社会はある種の洗練を目指し、合理的なシステムや科学技術に軸足を置くようになる。だがかねてから書いてきたが、日本では国立公園がひとつの縮図になっているように、合理的な洗練に至っているわけでもない。先人たちが信仰やロマン、生活のなかで切り開いた登山道も、素朴で忍耐強い人々に取って代わるべきシステムや科学が育つ兆しも薄いまま、荒廃しつつある。欧米への対抗心で作り上げた高度成長期の活況は明確なビジョンを持てぬなかで過去のものとなり、人間同士が遠く、自然との関係性も希薄な現実のなかにいる。素朴でもあれず、洗練にも至れないというのは辛いものだ。
もっとも、僕はなにかを美化したいわけではない。ミャンマーの貧困も、日本の道迷いも切実だ。ヤンゴンなどの都市部では人々がより良い明日に焦がれ、急激な変化がもたらされている。10年前は銀行が破綻し、闇の両替所しかなかったものが、いまではATMが出現し、多くの人が中国製のスマホを携える。辺りは外資による建設ラッシュだ。伝統的な生活感は突如﹁古いもの﹂になり、純粋な憧れと、欲望の闇が紙一重に交錯する。だが結局は経済も技術レベルも、幸福を図る尺度にはなり得ないのだろう。得る分失い、失う分得る、こうしたことの繰り返しだ。
願わくばすべての人がほんの少しの「自分であることの誇り」と共にあれればよい。そう思うばかりだ。