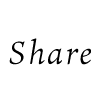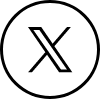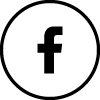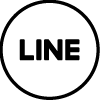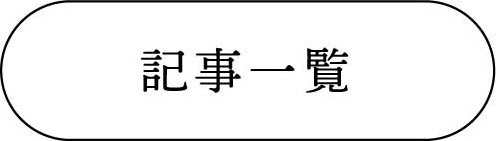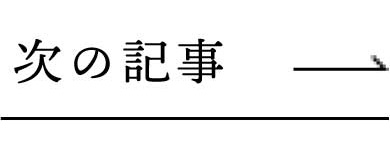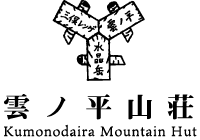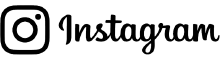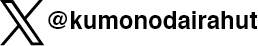山と僕たちを巡る話
第28回
これからの話
北アルプスの最奥、黒部・雲ノ平での暮らしから垣間見える世界。
来るべきオンシーズンに向けて、オフシーズンの間に準備しなければならないこと。
雲ノ平から下山して2カ月。今年は寝ても覚めても、日常の二文字が遠い。
気がつけばあたりではクリスマスイルミネーションが明滅し、2020年という迷宮のような季節に別れを告げるべく、人々が師走の街を忙しなく行き交っている。
だが、多くの人がうっすらと感じ始めているだろうが、コロナ禍はおそらくそれ単体で終わるものではない。コロナ禍が引き金となり顕在化した、自由経済や情報化、資本主義、民主主義、都市世界の脆さといった社会課題は、20世紀が溜め込んだ壮大な歪みともいうべきもので、良くも悪くも不可逆的に、僕たちを次なる冒険の時代へと押し流して行くだろう。ペストが大きな痛みとともに中世の闇を清算したように、僕たちは新しい時代の光を見出すことができるだろうか。願わくばこの混沌をエネルギーに転換して、希望のある方向へと歩みを進めたい。
山の世界でも、コロナ禍によって近年深刻化しつつあった山小屋事業の持続可能性や国立公園の維持管理に関する諸問題の危機感が急速に高まり、登山業界および行政、メディアを巻き込んでさまざまな議論が始まりつつある。
これまでは団結して意思表示をするようなことは極めて稀だった各地域の山小屋組合も連携し、行政に対してこの事態への対策(※1)を求める動きを活性化させている。昨年のヘリコプターの問題によって緊張感が高まっていたこともあり、今回ばかりは行政も本腰を入れて国立公園の管理体制の見直しに取り組む姿勢を見せている(※2)。
しかし、行政が対策に動けば早期に事態は収拾するかといえば、過大な期待はできない。なぜなら、コロナ禍自体は駄目押しをしたにすぎず、一連の問題の根幹ははるかに根深く、長い期間にわたって蓄積してきた構造的な問題に起因しているからである。そして構造的な問題というのは「金」の問題ではなく「人間」の問題なのである。
そもそも日本の国立公園の管理体制が脆弱なのは、歴史的に世論が自然保護やアウトドアレクリエーションの公益性に関心を向けてこなかったからだ。このことで国立公園を取り巻く人材や予算が著しく不足し、学術研究も低迷し、世論を喚起するための現状発信も欠乏している状況であって、その空白のなかである種の隙間産業的に発達したのが山小屋だった。
見ようによっては社会の無関心が山小屋の「なんでも屋」的な業態を生み出したのであって、その山小屋が困ったからといって、人材不足の行政が肩代わりをできるわけではなく、コロナ禍によって多くの業種が疲弊しているなか、世論が直ちにこの問題を社会的な責務として認識し、大幅に予算を確保するということもないだろう。
また、万が一政治的な駆け引きで予算だけは引っ張ってきたとしても、それを現状に即して有効に配分できる人材や機関は本当にいない。現状把握をしないままでは「使うこと」が目的化すれば、俗にいうバラマキに発展する。優先順位をつけられず、問題の規模を測れないからである。山小屋の経済支援ということを思い描いても、アクセスの良し悪し、規模、山域の人気、経営能力によって山小屋の経営収支の在りようは千差万別であって、もとより兼業でなければ成り立たない個人事業もあれば、従業員を複数名抱える優良企業もある。いかなる根拠、どういう水準で山小屋は維持されるべきなのか、どこまでが個人の努力の問題で、どこからが公共的な制度に委ねるべきなのかを見極めるだけでも、膨大な作業を要するだろう。

いまは新しい人材やアイデア、世論をも巻き込んだ形のコミュニケーションの強化、複雑な知恵の輪を解くような熟議、そして目的意識の共有こそが必要なのだ。
これまでも書いてきたように(本コラム13~16話参照)、日本の国立公園は特定の組織が絶対的な権限を持って管理する仕組みではなく「地域性公園」といって同一の土地に対してさまざまな関係主体が混在し、協働関係を築くことで管理して行くという構図になっている。
となれば、関係者同士が関わるなかで学び合い、相乗効果を高めて行くようなコミュニケーションのあり方こそが要となるはずだが、いままではむしろ絵に書いたような縦割り社会で、協力はおろか、組合ごと、県や市町村ごと、省庁ごとの既得権に捕われて、たがいに見て見ぬ振りをするかのような関係性が支配的だった。協議会などを開いても、行政側のメンバーに日常的に山の現場を訪れる人材がほとんどおらず、めまぐるしく異動を繰り返す人事制度も相まって、いつの間にか形骸化してしまうという悪循環だった。そしてなにより、共有されるべき目的意識が曖昧なのである。
いまは既存の関係者だけで内輪的に責任の所在を議論する段階ではなく、社会・世論と向き合いながら、大きなムーブメントとして今後の世界に「自然の価値」をどう位置づけ直すことができるのかを考え始める段階なのだ。
山小屋業界も、コロナがあろうがなかろうが変わらなければいけない時代になっていたことを思えば、まずは自分から、山小屋という仕事の可能性を最大限引き上げる努力をして世論を惹きつけ、ムーブメントの原動力になっていかなければならないと思う。
次回は、今シーズンの経験から得られた新しい山小屋のあり方の構想などへと話を展開したい。
※1)山小屋が担ってきた登山道整備などの業務の行政による直接的な関与、山小屋への各種支援など。
※2)北アルプスでは、登山インフラの維持管理に関わる多くの役割を民間事業者である山小屋が担ってきたために、山小屋の危機が国立公園の持続可能性にも直結してしまうというのがこの問題の背景。