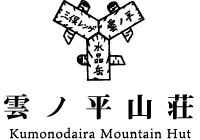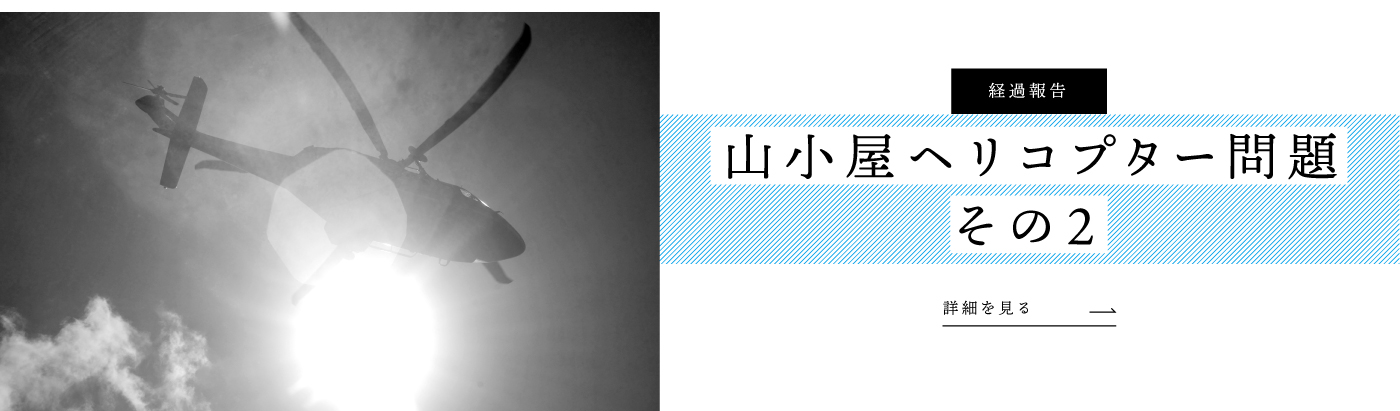【拡散希望】
登山文化の危機!
山小屋ヘリコプター問題
リポート:伊藤二朗
北アルプスの山小屋「雲ノ平山荘」経営者。1981年生まれ。東京都出身。幼少より黒部の源流で夏を過ごす。2002年に父・伊藤正一が経営する雲ノ平山荘の支配人になる。2010年、日本の在来工法を用いた現在の雲ノ平山荘の建設を主導し完成させた。
6月末のある日、T航空の荷上げを翌日に控えていた僕たちは一本の電話を受けた。「ヘリが全て故障したので、当面荷上げはできません」。ここから今回の騒動は始まった。
まず断っておきたい。僕自身が当事者としてあまりにも深く関係してしまっている問題のため、表現は慎重を極めなければならないことだが、山小屋や日本の国立公園の大きな岐路にもなる事態なので、書きたいと思う。山小屋や国立公園、航空会社など、関係する全ての人々が建設的な将来に向けて一歩を踏み出せることを祈って。
かなり長い文章なのだが、ぜひご一読いただきたい。そして、ひとりでも多くの方に知ってもらうために、広くシェアしていただければ幸いだ。
2019年7月下旬現在、多くの山小屋の現場で重大な異変が起こっている。営業物資、生活物資が突如として届かなくなったのだ。数年前から主要なヘリコプター会社のA社やN社が山小屋の物資輸送から事実上の撤退を示唆し、大幅値上げや契約拒否などに踏み切っていることは問題として顕在化していたが、ここにきて現状北アルプスの8割方の物資輸送を手掛けている、最後の砦とのいうべきT航空が、一昨年来相次いだ事故やそれに誘発された人材流出、直近の機体トラブルなどによってついに機能不全に陥ってしまったのである。
その影響は未曾有である。
先述の故障の連絡から2週間ほどでヘリコプター1機が復帰し、徐々に仕事をこなしつつあるとはいえ、悪天候もあり広大なエリアに散らばる数十軒の山小屋が必要とする物資を安定供給する目処は依然立っていない。
僕の知る限りでも食料が届かずに客食を提供できない小屋、燃料が切れかけている小屋、営業開始半月経っても物資が届かない小屋、冬季解体して夏に再度組み立てるはずの施設が建てられず営業開始が遅れている小屋など、あらゆるレベルで影響が広がっている(全ての情報を網羅できるわけではないが、7月下旬現在、ほとんどの小屋で営業ができない状況は解消されたようだ)。当然雲ノ平山荘も例外ではなく、6月26日、7月10日、7月21日に予定されていた荷上げ物資の内、手元に届いたのは半分以下で、現場は相当に難しい舵取りを強いられている。
そして肝心な点は、例え当面の物資輸送の滞りが表面上は解消に向かったとしても、「山小屋ヘリコプター危機」とも呼ぶべき事態はまだ序章に過ぎず、今後この問題は際限なく拡大して行く可能性が高いということだ。目下1、2ヶ月の短期的な危機の度合いが黄色信号であるとするなら、1年~10年といった中期的な危機の度合いは限りなく赤信号に近い。今回の騒動を呼び水に、今後ヘリコプターによる物資輸送を受けられなくなる山小屋が続出する可能性があるのだ。
更に言えば、これはただの「山小屋の経営危機」や「悪天候の影響」、「ヘリコプター会社の内憂」というような単純な話ではなく、今年の夏の登山ができる、できないという話でもない。今まで潜在的な危機を認識しながら棚上げにし続けてきた「日本の国立公園、登山文化の持続可能な運営システムの欠乏」という大きな問題が一気に棚からなだれ落ちようとしているのだ。
国立公園・
登山文化の危機
日本の国立公園、特に北アルプスでは実態として、山小屋(やその他民間団体)が多くの面で公共的な役割を担い、維持管理、運営に当たっている。公共性の高い部分だけを列挙しても、緊急避難施設であること、遭難救助、登山道整備、診療所の開設、登山者への食事及び各種情報提供など、実に多岐にわたる。
一方で環境省などの行政機関は予算が非常に小規模で、人材も少ない(正規レンジャーが北アルプス全域に5人)ことから現場に対して能動的に関与する仕組みをほとんど持っていない(これは、行政が国立公園の成立当初から自然保護的な発想で直接現場に関与する立場ではなく、観光政策としての旗振り役、許認可業務などが中心の立ち回りだったことによる。北アルプスでは開拓活動からして山小屋創業者や民間団体が牽引し、必然的に「民間事業」主体の国立公園になった)。
しかし、今まで行政が山小屋の公共性を正式に評価し、制度に落とし込むことをしてこなかったため、いざ山小屋が存続に関わる重大な問題に直面したとしても、山小屋の運営を公的に支える仕組みや法律が存在しない。山小屋の危機が国立公園の運営の問題に直結してしまうのはそのためだ。
今回のケースを少し拡大解釈して説明すれば、例えば何らかの理由でヘリコプター会社が山小屋の物資輸送から全面的に撤退、あるいはトラブルでヘリコプターを運行できくなるとする。それによって山小屋が経営困難になり、結果的に国立公園の運営に重大な支障をきたすとしても、いかなる合理的な解決策もない。この問題を扱う法律自体が存在しないのである。山小屋の破綻は民間事業者の個人的なトラブルという位置付けに過ぎず、ヘリコプター会社に山小屋の物資輸送をし続けなければならない義務はなく、トラブルに見舞われたヘリコプター会社に変わって他のヘリコプターを行政が手配するなどの代替え措置も存在しない。
各地で登山道の荒廃が山小屋では対処しきれない状況になっても、行政にはほとんど打つべき手立てがないことと同根の問題だ。つまり、行政にこそ公共性がないのである。かくして、国立公園の運営は究極的にはどこにも担保されていない。
山小屋と
ヘリコプターの関係
1960年代初頭以降、ヘリコプターは山小屋運営の絶対的な生命線になった。それ以前は人が背負える範囲内の物資で山小屋を建設し、生活物資や食料を確保し、人力だけで開拓活動全般を行っていた。食料は宿泊者がある程度持参するのが慣習であった。それが60年代初頭のヘリコプターによる山岳地への物資輸送が実用化され、全てはそれを前提として発展することになった。
歩荷一人60~80kg背負って雲ノ平まで2日かかる仕事が、一回500~1,500kgを往復15分足らずで行き来するヘリコプターに取って代わられた。経費は大幅に削減され、各地の山小屋建築も飛躍的に近代化され、発電機、電話、無線網、冷凍食品やビール、ジュースなどが当然のように備え付けられるようになった。近年のバイオトイレやソーラー発電システムの導入なども言わずもがなだ。
その山小屋の利便性に合わせて定番化したのが、現在の大衆的な登山のあり方である。遭難対策の連絡網や潤沢な食糧事情、寝具の提供、診療所の設置など、登山のリスクを最小限にする仕組みが行きわたり、はじめてツアーや初心者、高齢者の登山が可能になる。今となっては、ある程度現代的な生活環境が整ってはじめてスタッフの雇用も成立する。
見方によっては日本の国立公園ほど登山の敷居を下げた環境は稀なのかもしれず、現在の山小屋のスタイルは過剰サービスに映る人もいるかもしれないが、事実としてこの50年の登山環境を成立させてきたのは紛れもなくヘリコプターであり、現状の日本の登山は「山登り」文化であると同時に「山小屋」文化なのだ。しかし、それはヘリコプターによる物資輸送が消滅した途端に脆くも崩れ去る諸刃の剣に他ならない。
また、公的に経営環境を支える仕組みがない以上、山小屋は自らの存続・発展を図るために、民間事業者としてあらゆる手段を用いて利益を確保する必要があり(※1)、自然保護的な公共性の側に立ってオーバーユースや大型ツアー、高齢者登山などの問題に正面切って取り組む思考は芽生えづらい。日本の国立公園が自然保護の発想が乏しい一方で、「マスツーリズム的」であり、メディアや行政が自然を訪れるのとほぼ同等に、山小屋を訪れるための情報発信、公共事業を展開しているのも「民間経営の国立公園」であることによる。公共性と商業性がある種の矛盾を抱えながら混在しているのだ。
(※1)
山小屋の収益はその多くが設備投資に備えるべき性質のものだ。どれだけ稼いでも建て替え工事などがあるとゼロに戻り、あるいは借り入れを完済したころにまた建て替えの時期になる、この繰り返しだ。物資輸送費、建設費が急騰している昨今、事業として成立しない施設も増えるだろう。
山のヘリコプター事情
山小屋のヘリコプター事情の風向きが変わり始めたのは雲ノ平山荘を建て替えた2010年頃からだったと思う。2011年の東日本大震災が何らかの形で影響を及ぼしたのかとも思われるが、それまでは前出のT航空が比較的大きなシェアを占めていたとはいえ、4社ほどがそれなりに正常な競争原理を働かせながら共存して北アルプスの山小屋の物資輸送を行っていた。それが2010年頃からA社、N社、S社などが山小屋の物資輸送を急速に撤退方向に舵を切り始めた。
当時、雲ノ平山荘で契約していたN社も突如として、山小屋の物資輸送から撤退したい旨を公言するとともに、3年間で段階的に物資輸送単価を倍近くに引き上げることを通告してきた。交渉しようにもにべも無く、一方的な通達である。その際N社の担当者が話していたことが、端的にその後の展開を物語っている。
「時代とともに農薬散布や林業などの大口の民間事業がなくなり、ヘリコプターの需要自体が限られる中、今までのように広く浅く収益を上げる方針は変更せざるを得ない。これからは電力会社の事業や公共事業などの単価が高く、大型工事にターゲットを絞る方向になる」
おそらくこの方向性はヘリコプター業界にとってはある種必然的とも言える経済判断であって、生き残り戦略でもあるのだろう。ことさら、山小屋の物資輸送は気象条件が厳しく円滑に仕事をこなすことが難しいため、ハイリスクローリターンの典型でもある。その後はN社と前後してA社、S社なども同じ方針を打ち出しはじめ、他社に契約を断られた山小屋が続出し、結果的にT航空に過剰とも言える山小屋の物資輸送のシェアが集中することになった。
歴史的に山の航空事業にプライドを持って臨んでいるT航空としては、可能な限り山小屋の仕事を引き受けるべく、技術的に難しい山の物資輸送に対応できるパイロットや整備士の育成、山小屋に配備できるヘリコプターの機体の確保などを進め、現に雲ノ平山荘も長い話し合い期間の末に2017年からT航空に物資輸送をしてもらえることになった。
しかしその矢先である。T航空の大型ヘリコプターが墜落事故に見舞われ、そこから大きく計画が狂うことになってしまった。T航空の関係者曰く、「もとより10ある仕事量に対して10の人材と機体でかろうじて対応していたところに来て大型機の喪失に加え、様々な経緯によって人材を失う流れとなり、その後は変わらずに10ある仕事に対して5や6の対応力になってしまった」のだ。
そもそもヘリコプターがひとたび事故に見舞われると航空局から厳しいペナルティーや制限を課せられ、ただでさえ身動きが取りづらくなってしまう。
このことを考えるほどに山小屋の物資輸送を手がけるのがT航空一社になってしまっていること自体がそもそも計り知れないリスクなのである。
もしシーズンの途中にその唯一の航空会社が事故に見舞われてしまったとしたら、即取り返しのつかない事態に陥ってしまう。誰しもが容易に予想し、潜在的なリスクを感じていたし、近年は山小屋の会議などでも行政に対して山小屋の物資輸送への介入の可能性を検討するよう訴える声も上がっていたのだが、何ら解決の糸口を見出せないまま今年の状況に至ってしまった(※2)。
通常にこなすだけでもギリギリのスケジュールで相次いだ機体トラブル、悪天候により、ドミノ倒し的に過密スケジュールがパンクしたのである。まだ完全な破綻をきたしたわけではないが、恐らく大多数の山小屋関係者は解消しようのない危機感を持って事態を注視しているはずだ。
そして現実問題としてT航空としても「現状のままではほぼ間違いなく、近い内に山小屋の契約を整理、削減せざるを得なくなる」という。山小屋の仕事からいち早く距離を置いたその他3社は、まだごく少数の山小屋の仕事を行なっているとはいえ、新規の仕事は受け付けない状況だ。今後の展開として、もし数多くの山小屋がT航空と契約を更新できず、あるいは作業量を大幅に制限されて営業が危ぶまれても、現状取り得る有力な選択肢は皆無だ。まさに今が社会をあげて行動を起こすべきターニングポイントなのである。
(※2)
山小屋が共同体・組合として一体的にこういった問題に取り組めない、ということも根深い問題だ。発信力のある有力な山小屋ほど安泰であったり、一部地域で既得権を囲い込んだりする傾向もあり、結果的に強者の論理が登山文化、国立公園全体の問題をうやむやに「棚上げ」してしまうことも多い。ヘリコプターの問題も、潜在的な危機は大多数の山小屋が認識していたが、問題に直面した山小屋だけが水面下で打開策を模索したり、小声で悩みを打ち明ける程度の展開にしかならず、山小屋全体の動きには結び付けられなかった。
これも「民間経営の国立公園」の弱さで、日本では自然保護思想や国立公園全体の経済合理性など、関係者を精神的に団結させる理念や合理的な計画性などが希薄であり、地域や個人ごとの経済的利害が先行してしまっていることが強く影響している。いずれにせよ、この状態では、栄える山小屋、地域とその他でいよいよ二分化が進み、全体で機能していた登山文化は衰退して行くだろう。
また、山小屋のみならず、市町村ごと、県ごと、国が共通の利害に対してでさえ連動せず、打ち消しあってしまう日本の社会構造、精神構造も深刻な弊害だ。全体で解決に導く、相乗効果を生み出す、といった発想や仕組みがない。
問題の核心と提案
一つ言えることは、ここに来て悪者探しは全くもって意味がないということである。要するには国立公園、日本の登山を持続可能な形で成立させるための合理的な制度が存在していないことの問題なのだ。そして国立公園の現状を正しく評価するための最低限の知見やマンパワーが行政側にないことが問題を常に迷宮入りさせてしまう。山小屋の業務やヘリコプターによる物資輸送はどの要素が、どの程度公共性を持っていることなのかを正しく評価し、安定的に存続できる仕組みを作ることが急務だ。個人的意見に過ぎないが、以下にこの問題の打開策を提案したいと思う。
◎現状ではヘリコプター会社が山小屋の物資輸送を無条件でやめる自由を持っており、公共インフラとして維持する義務が何ら存在しないことが問題の根底にあるため、制度として一定の義務化を進める必要がある。そのためには複数のヘリコプター会社を参入させる必要もある。
◎同時に民間事業者であるヘリコプター会社が上述のように「ハイリスクローリターン」な山小屋の仕事を敬遠するのは経営判断として必然的なことでもあるため、行政がヘリコプター会社に対して助成金を出し、事業として持続可能な体制を構築する。また、物資輸送単価が山小屋の存続にとって過剰に高騰した場合には、単価を一定に抑える仕組みを作る。これは離島のフェリー便と同じ構図かと思う。(※3)
(※3)ヘリコプター業界関係者によれば、価格については80年代に起こった航空会社同士の「山小屋作業争奪戦」とも呼ぶべき過当競争が影響しているようだ。値段を下げられるだけ下げた結果が現在も響いていて、他の事業に比べると今だに山小屋の物資輸送単価が非常に安いという。現にT航空以外で荷上げしている山小屋の料金は公共事業並み。「価格」も今後展開するうえでの大きな要因だろう、とのこと。当然「公共事業」の単価が過剰に高く、競争力に劣る民間事業者を圧迫している可能性もある。いずれにせよ、収益が上がる事業にターゲットを絞るのは経済原理としては真っ当であり、そこにこそ山小屋の公共性の議論が必要になる。
◎また、緊急時の対応として行政が手配し得るヘリコプターを動員し、事態の収拾にあたる。これは災害時の人道支援体制と同じ構図かと思う。現に国立公園を訪れる登山者の救助を主な目的として配備されている県警察などのヘリコプターには多額の予算がついていることを考えると、有償を前提としてでも、国立公園の運営の安定化に資するヘリコプターがあっても良いのではないだろうか?
◎恒久的な措置としては、山小屋、ヘリコプター会社の業務のどの部分がどの程度公共性があるのかを見極めるのが恐らく一番難しい作業になる。一口に山小屋といっても様々な業態があり、現に格差と呼ぶべき状況も存在しているからだ。
例えば人里からのアクセスが良く人気のある小屋はヘリコプター代を始め各種ランニングコストが安く、営業期間も長い。登山者は訪れやすく、人材を雇用できる経済的な体力に恵まれ、設備投資、広報などに力を入れる余裕があり、登山道の整備に割ける労力、時間もある。
アクセスの悪い零細の山小屋は正反対だ。ヘリコプター代を始め、各種ランニングコストも高く、営業期間も短い。登山者は訪れづらく、人材を雇用できる経済的な体力が乏しく、設備投資、広報などに注力する余裕もなく、登山道整備などにさける時間、労力共に限られる。
結果前者は人気を博し、かつ宿泊料金を高くしても納得され、後者は設備も刷新できず、一般的なサービス業の尺度に当てはめると宿泊代も上げづらく、スタッフの給与も開きが出てくるなど、自動的に格差は開いていく(もちろん自助努力で付加価値を高め、補える要素はたくさんあるとはいえ、埋めがたい差があることは事実だ。現に条件の悪い小屋は意欲も低下しやすく、世代交代も難しくなっている。)。
具体的にヘリコプター代でいえば、例えば前者が1回につき5万円から10万円に値上げされたとして、同じ値上げ率を奥地の小屋に当てはめると、元から1回10万円払うところを20万円払うことになる。ヘリコプターの単価と、山小屋の公共性、さらにこの「格差」の因果関係を考慮するとすれば、ヘリコプター会社に助成金を出した上で、山小屋の物資輸送単価を一律に設定するというのがフェアかもしれない。
◎ヘリコプターが運行しないことによって通常営業ができなくなるというのが直近の危機だが、準じて思いやられるのが、老朽化した山小屋の再建が不可能になるリスクだ。山小屋の最も重要な役割は建築物、避難場所としてその場に存在していることに他ならない。しかしその建設費はもとより人里の建築の2、3倍はかかる莫大なもので、立地にもよるが山小屋の収益の大半は建て替えや大規模改修などによって吹き飛んでしまうといっても過言ではない。
10年前に雲ノ平山荘を建設した際でも、ヘリコプターの物資輸送だけで4千万円かかったが、今同じことをしようとしたら物資輸送代だけで1億円を超えてしまうだろう。また、現状スケジュール通りにヘリコプターを安定的に運行してもらえる可能性はかなり低く、雪がない時期に工事を完結しなくてはならない山小屋建築のタイトな計画性を考えると実現そのものが困難になる。
さらに近年の建築費の高騰も加味すると借り入れの返済に何十年かかるかわからない。こうなれば山小屋建設自体が採算の取れない事業となり、民間事業として成立させるのはほぼ不可能である。そもそも銀行が話に応じないだろう。
◎ドローン台頭説を唱える人が沢山いるが、僕はそれはまだ空想の域を出ないと思う。たとえ近い将来に重量物を運べるドローンが実用化されたとしても、結局はヘリコプターと同じ顛末を迎えるような気がしてならない。
今は小型機が主流なのでドローンの操縦に関して明瞭な免許・メンテナンスの制度もないし、各種法的な規制も弱いが、恐らく100kg以上運ぶ巨大な飛行物体になった瞬間にヘリコプターと同等の法的な制約に組み込まれるだろう。ましてや遠隔操縦で、通信の安定しない山岳地でのことだ。技術の確立、安全性の確保と法体系の確立には長い時間を要するだろう。
結び
これまでの山小屋のビジネスモデルが戦後の人口増加による国内需要の爆発的な拡大や高度経済成長、ヘリコプター事業の黄金期に支えられたものであることを考えると、各種条件が崩壊しつつある中、これを恒久的なビジネスモデルとするには無理があると思う。
ではヘリコプターの物資輸送をなくして、歩荷の時代に戻れるだろうか(それも職業歩荷もいない現代で、奥地の山小屋ほど早くにその選択を迫られるかもしれない)。食事は保存食で、ビールなどは販売しない、灯りはランプで賄い、スタッフの風呂は薪で、多額の補助金を投入して作ったバイオトイレは汲み取りに戻す、ということでよいのだろうか。
そもそもどの程度まで売り上げが減少することに、民間事業として持ち堪え得るのか。民間事業として成り立たなければ山小屋は自然淘汰されていくだろうが、国立公園の運営としては、どこまで「山小屋の消滅、自炊小屋化」などは許容すべき問題なのか。多くの山小屋が先祖返りし、国立公園、登山文化によって得られた経済効果が大きな打撃を受けるとして、それがヘリコプター会社の経営判断に委ねられてしまっている状態は社会として理にかなっているか。
人材不足の環境省が山小屋の経営に、大なり小なり介入できるだろうか。メディアはあくまでも受け身の姿勢で「山小屋不在で山を歩く事」に特化した情報発信、あるいは生き残った山小屋にターゲットを絞り込んで仕事をし続けられるだろうか。どれくらいの登山者が食事や寝具の提供が得られず、遭難対策のネットワークもなく、登山道も整備されていない山登りに適応できるだろうか。
これらは極論の一種である。しかし今までは時代の成り行きに任せてなんとなくやりくりしてきた事々を、今後は登山文化に関わる全ての人が明確に取捨選択しなければならないだろう。各種サービスのレベルや登山道管理の責任の所在なども含めて、どのレベルで山小屋の公共性を評価し、持続可能な仕組みとして登山環境、国立公園を再構築していくのか、具体的な答えが必要である。
その緊急の課題が、今僕たちが直面しているヘリコプターの問題だ。
誰が、どのように山小屋、登山者に物資を届けるのか?