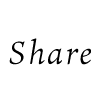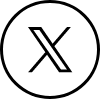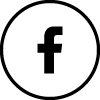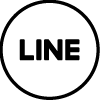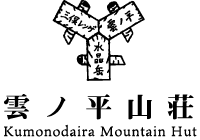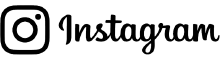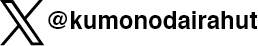「伊藤正一・志づ子ご夫妻と私」そして、これからの私のとり組むべき山々
とある季節の情景
ななかまど17号(2014年発行) 掲載記事 - 伊藤二朗=文・写真
まだ景色の半分以上が残雪に覆われた七月初旬。間近に迫った営業開始に合わせて僕たちは各方面の登山道の開通作業に出かける。今回はその折に毎年見る美しい景色のことから書きはじめてみようと思う。
雲ノ平山荘から奥スイス庭園を通り、前方に聳える雄大な薬師岳と、眼下に黒々と広がる黒部の谷を見晴らしながら、高天原に向かう登山道を30分ほど進むと次第に樹林帯が現れてくる。この時期は道の大半が雪に覆われており、奥スイス庭園の辺りはまるで白い丘陵の上を薬師岳に向けてまっすぐに続く道を歩いているような感覚がして気持ちが良い。樹林帯が出現し始めてほとんどすぐに、登山道は“雲ノ平の森の道”に入っていく。この道は今から9年ほど前(2005年)に当時は草原の急斜面についていた道が荒廃してしまった事から、僕たちがすぐ西側にある樹林帯に付け替えた登山道である。積雪に押された形に道にしなだれかかっているななかまどの枝をかき分けて、森に入ると雪はすっかり融けていて、オオシラビソやトウヒの黒い樹影の中に、鮮やかな新緑を芽吹かせたダケカンバの梢が高山に遅い春の到来を告げている。それでもこの時期はまだ、一見すると下草もまばらな森の中は色彩と言える色彩はほとんどなく、谷から吹き上げる風も、残雪の冷気の中に時たまなまぬるい空気を運んでくるような、季節の端境期のことである。森の中は、どことなくガランとしている。しかし歩き始めてややもした頃にふと、視界の片隅に何かしら鮮やかな印象が飛び込んできたような気がして辺りを良く見回してみると、すぐ足元から、そこにも、あそこにも、と言った具合に小さな紅色の花の群落が点在しているのを見つけるのだ。イワカガミの花畑である。それぞれが倒木の上や、岩に付いた苔の上や雪融け水の流れの中にほんの小さな範囲の群落を作り、小指大にも満たない紅い花を無数に咲かせている。森林限界を越えた草原の中では、この花はとかくアオノツガザクラやチングルマ、ミヤマキンバイなどの花たちとまぎれる様にして咲いている事がほとんどなのだが、ここでは見渡す限り咲いている花といえばイワカガミ達だけであって、その前にかがんでじっくりと眺めていると、不思議と、何やらとても贅沢な花畑に居るような心地がしてくるのである。花と言うものも環境が変わるとこんなにまで鮮やかに印象を変えるものかと、まるで偶然街で見かけた顔見知りの少女が、普段とは全く違う大人びた魅力を湛えている事に気付くかのような、淡い感動を覚えさせられるのだ。そしてまた小さな花畑から顔を上げると、依然深閑とした森が広がっている。

時に僕たちは、道伝いの木杭に添わせてロープを張ったり、傷んだステップを直したりしながらだんだんと森を下っていくのだが、500mほどあるこの森の道をちょうど半分ほど下った場所に、樹齢500年は越えているだろうと思われるトウヒの老木がある。黒々と聳える樹容は、見るものに自然とこの森の主である事を知らしめる悠然たる風格を漂わせており、遥かに伸びる枝葉は森の高みで大きな両腕を広げ、他のか細い木々を包み込んでいるかのようでもある。僕たちはいつからとも無く、その木の前を通りかかる度に立ち止まり、日々の営みの感謝を告げる事にしてきたのだが、殊更毎年シーズンのはじめと終わりには、様々な思いを寄せて挨拶をする事にしている。“今年もお会い出来ましたね。どうぞよろしくお願い致します。”または“この冬もどうかご無事で”と。
ただ、僕はこの老木のことで近年気付いた事がある。 それはこの木の生身の生き物としての容態とも言うべきことで、それまで僕の目には、大きくて力強い物の象徴のようにさえ映っていたこの木が、良く見てみると幹の内部は大きな洞(空洞)になっており、必ずしも5体満足な状態ではないらしいのだ。尤も洞があるからと言ってすぐにどうなると決まったわけではないのではあるが、仮にこの木が500年間生きてきたとして、もし今後僕の生きている内に死んで、倒れるようなことがあったとしたら、それはまた何と言う大きな巡り合わせだろう…、その事に思い当たってからというもの僕は、この老木に会うたびに、なぜともなく、生きていることに対する幻想と錯覚についての自問を巡らせるようになった。そもそも僕が生まれて30数年になるわけだが、自分にとっては記憶の全てである30年と、この老木や、雲ノ平という土地が経験した30年、あるいは人類の世紀における紛然たる30年は、互いに何か共有するところがある…というか共感する事を許されている存在なのだろうか…、毎年深い縁あって訪れるこの土地で、気付けば小さな木は着実に一年、一年と成長を遂げ、老木は一歩ずつ天寿を迎えつつある。また、自分もいつのまにか年を重ね、我が父に至ってはこの老木に近い領域の住人である。初代の雲ノ平山荘に使った木を切り出したのもまた、この森であると聞く。今でも良く探すと潅木の間にポツ、ポツとそれらしい苔むした切り株を見つけることが出来るのだが、その懐かしい山小屋も既に影も形も無く、当時木材を切り出した職人たちとて多くは天上の人となっていることだろう。忘れ形見はその切り株だけだ…もしかしたらその廻りにも、イワカガミが咲き乱れているかもしれないな…などと思ってみたりすると、何だか少し侘しいような、温かい気持ちがして来るものだ。
きっと500年も、あっという間の事だったのであろう。そして老木も自分も、同じように1年を、1年として生きている。大自然だから強く不動で、一人間だから弱く、移ろいやすいなどという事も―あるいはその逆も―本当は幻想に過ぎないのではないか、と思うことがある。
そうこうする内に、僕たちはあらかたの作業を終え、森の道の出口付近に到達している。この出口付近は雪解け水が小さな水流を成して、草原から森の中に流れ込んでいる場所であって、雲ノ平ではあまり豊富にない“アマナ”と呼ばれる旨い山菜がいくらか収穫できるという事があって、毎年この機会に―これまた或る種の儀式のようにして―ありがたく頂戴するのだ。今夜はお浸しにしようか、味噌汁に入れようか、それとも天ぷらにでもしようか。その後本日の作業の締め括りとして、高天原方面に向かって2,300mほど雪渓の上に紅ガラで道しるべを付け、ようやくひと息ついてお茶などを飲みながら見上げた視線の先には、水晶岳が西日に照らされて金色に空に浮かび上がっている。
奥スイス庭園の雪の斜面を登りきった頃、東の空では宵闇が藍色の帳を下ろし始めている。日中は白い丘陵のようであった雪渓は蒼白く影に沈み、折からの冷たい夕風に晒されて辺り一面から白い靄を立ち昇らせている。背後を振り返ると、真っ赤な落日が今しも薬師岳の稜線に沈もうとしている。何もかもはただ生きて、生きて、生きている。何万年という歳月がこの夕風と共に過ぎ、また無心に日々が始まって行く。
“全ては尽きることのない祈り…。”
ふとそんな気持ちが胸裏をかすめる。
以上が、ほぼ毎年繰り返される、とある季節の情景である。