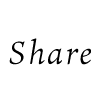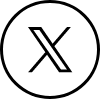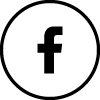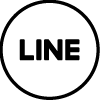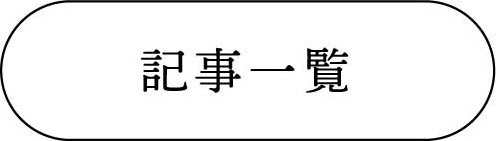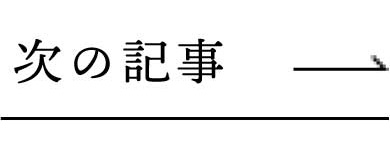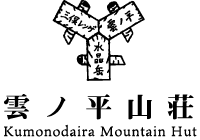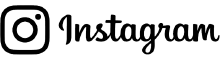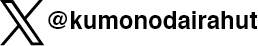山と僕たちを巡る話
第29回
これからの話 その2
北アルプスの最奥、黒部・雲ノ平での暮らしから垣間見える世界。
さまざまな価値観が刻々と変貌するなか、山小屋の将来あるべき姿を見つめなおす。
さて、年も明けたが、コロナは依然猛威を振るっている。
とはいえ世界の混乱だなどと大きな話をしてもはじまらないから、自分の足元の話を続けよう。どんな困難な状況にあっても普遍的に変わらないことはあると思うが、そのひとつは「必要とされないものはやがて忘れられる」という冷徹な法則だ。山小屋は果たしてどれほど必要とされているだろうか。
これからその話を展開する前に、もう少し山小屋の現状について考察してみたい。
そもそも、従来の山小屋のビジネスモデルは昭和の観光産業への状況依存的な業態だったと僕は思っている。開拓時代はさておき、ヘリコプターが飛び始めた1960年代~2000年代中盤までは、増え続ける国内人口、定期的な登山ブームで宿泊者はあふれ、ヘリコプターの安価で潤沢な作業供給、安い建設費、 低賃金でもスタッフが集まる好景気、テント装備の未発達などに依存しつつ、サービスの質や経済合理性を強く意識せずとも山小屋経営は成り立つ時代だった。純粋に民間事業として考えると、競争原理は働かず、山が人気である限り人は来るという、ある種の独占的な環境で、シビアな経営努力はとくに必要ではなかったともいえる。
こうした条件がすべて消滅しつつあるいま、コロナ禍の有無にかかわらず山小屋は岐路に立たされている。国内需要の縮小(※1)が既定路線であるからこそインバウンドの議論にもなっていたが、コロナでそれも見通しが立たない以上、より革新的なアイデアが求められる。物価の上昇に対応した料金設定にするのはもちろんだが、料金を上げればサービスの質を根本的に向上しなくては、快適性を増したテント泊山行の需要に負ける。10㎏以下の荷物でゆとりを持ってテント泊山行を楽しめる状況で、なにが悲しくて混雑して殺風景な山小屋に大枚をはたいて泊まるというのか。
「悪天時、遭難時の避難場所」という消極的な動機を振りかざしても商売にはならないし、いくら登山道の維持管理や遭難対策における山小屋の公益性を唱えても、世界中で山小屋がない山域でもそれなりに登山文化が息づいていることを考えると、登山文化=山小屋でないのは自明だ。日本では行政が自然保護の受け皿にならなかったために、個人が担う構図ができたわけだが、その構図自体は持続性の観点から見ても執着するべきものではない。さらに料金の問題になると綺麗ごとは通じないわけで、ワーキングプア世代は必然的に山小屋泊から離れていくだろう。
これからの山小屋存続の可能性は、前回も触れたように金ではなくさまざまな形で「人間」を育て、繋げることによって文化・科学の総合的な基地としての役割を担うことに見出すべきだと僕は考えている。

学術研究、教育、ボランティアの拠点であり、官民学の交流の場であり、芸術やデザインの生まれる場所、アウトドアレクリエーションの基地、SDGsの理念に根ざした先端技術の実験場、自然と人間の接点で花開くあらゆる創造の基地として、山小屋には無限の可能性がある。そして、現場におけるコミュニケーションの多様な発展のなかで「地域制公園」の実践的な仕組みづくりへコミットする道筋も見いだせるはずだ。当たり前だが、社会を作るのは制度ではないし、一個人でもない、人と人の交わる力が社会を作るのだ。
業態は宿泊業と心中するような単一的なものではなく、今年の山小屋クラウドファンディングなどにもその可能性の端緒は見えたが、より社会に根を張る形、個人の所有の意識から文化的共有意識へと移行するなかで、複線的な資金調達のあり方をも視野に入れるべきだろう(※2)。
登山という概念が中心にあるのではなく、文化の発信拠点であり、自然のなかにある社会としての意志を育むことが必要で、それは非日常を楽しむという感覚から離れ、日常性のなかで自分たちの可能性を発掘するための健全な(ワクワクするような)野心に裏付けられるべきだ。これらを実現するためには、山小屋の居住空間が自然に調和するデザイン的な美しさを体現し「滞在したい」と思わせる環境であることも、ますます重要になるだろう。
雲ノ平山荘では、12年前から東京農業大学との植生復元活動、それにともなう官民学の協議会の開催や学者によるレクチャーの開催、メディア関係者との社会課題への連携や今年行なったアーティスト・イン・レジデンスなど、まだまだ小規模ながらもコミュニケーションの形の展開を図ってきたが、最近になってようやくその方向性について確信めいたものが感じられるようになってきた。
やはり異分野の人々が交わるごとに自らの視野も広がり、山小屋という「場」の持つ熱気が高まることを実感する。創造的に自然に接している人がその場にいるというだけで、登山者の視点や好奇心も変化していくのだ。
ある種の「量で稼ぐ」業態であった山小屋が、利用(量)によってすり減っていく自然公園管理の主体であることも矛盾だったわけだが、消費から創造へ、量から質への比重の移動を図るべき時期である。世界中で自然環境との共存が社会の最優先課題として叫ばれる今日、山小屋や自然公園が廃れる理由などまったくないはずなのだ。(続く)
※1)向こう40年で人口30%減。
※2)個人が多角的な事業を展開したり、ヨーロッパ的に山岳関係の組織が山小屋を運営するのも選択肢だ。